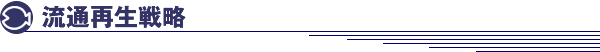第2章 小売業は人−人材育成こそ再生の条件
動機づけ理論ブーム
「人間機械論」の古典的組織論への反論として、組織を構成するメンバーは価値観や目的をもった人間であり、組織理論は「動機づけ」を中心とした人間関係論でなければならないという考え方が出てきた。経済の側からの論理でのみ展開された企業社会に、はじめて社会心理学、行動心理学という人間に重きを置いた考え方が導入されることになった。
C・I・バーナードは「権限受容論」を唱え、権威は組織の下位者(組織のボトムメンバー)が受容するかしないかが重要であり、上位権限説(組織のトップメンバー)は幻想にすぎないとした。
クリス・アージリスは官僚制組織に対する個人の葛藤の克服を目指し、「従業員個々人に課せられた統制は抵抗を生み、ついには企業をかたわ者にしかねない。一人前の従業員を欲求不満にし未成熟のままにさせている要因はフォーマルな組織、命令によるリーダーシップ、予算・報償制度にある」とし、民主的リーダーシップに基づく個人のパーソナリティを尊重した組織運営を提唱した。
ダグラス・マグレガーはX理論組織、Y理論組織を定義した。X理論は古典的組織論、上位下達の組織管理をもつ管理者スタイル、Y理論は「人間関係論」、動機づけを重視する管理者スタイルである。
これらの主張を要約すると、そもそも人間は機械ではない、組織は、個人の個性を尊重し、個人の目標をも満足させるものでなければならないとするものである。したがって、いかに個人の生きがいを組織と一体化させるかが重要であり、上からの強い統制・命令的リーダーシップ、上位組織のみの意思決定は「悪の根源」であり、意思決定への組織メンバーの参画、ゆるい統制、相互の話し合いによるリーダーシップが組織を運営するポイントであるということが理解できる。
| 前の項目 | 学者の組織理論 |
| 次の項目 | 合理性限界論 |
Copyright 2006 (C) Jericho Consulting Co.,Ltd.
本サイトの全ての文章、画像を無断で転載することを禁じます。