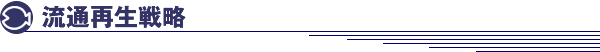古典的組織理論では、「組織のメンバー(従業員)は、受動的な機械であり、仕事を遂行し指示を受けることはできるが、自ら行動を起こし、影響力を行使することはほとんどない」と仮定した考え方である。かの有名なフレデリック・テーラーの「科学的管理運動」――人間は機械の付属物であり、本来的には人間というのは非能率的であるとして、人間の心理的側面よりも、むしろ機械化やオートメーションに関連させた――は、古典的組織理論の代表である。
この「人間機械論」が古典的組織論の一方とすると、他方は、L・ギューリックの研究に代表される「部門化理論」がある。これはアダム・スミス以来の、分業化こそ能率的であるとする考え方であり、ギューリックは、組織の活動を、多数の組織メンバーの間に能率的に配分することが重要であるとして「最適能率分割論」を主張し、分業による専門化を用いることの妥当性を述べている。
古典的組織理論をより発展させたのが、マックス・ウェーバーの「官僚制」、すなわちピラミッド型組織論である。この考え方は、「近代の諸問題の複雑性を克服していくには、専門化、分業化を柱とした官僚制組織が最も合理的である」ということを指摘した。ただし、ウェーバーは、古典理論が指摘しなかった「しかし、合理的であればあるほど、人間抑圧がタガとなって人間を締めつける」という危険について述べている。
1949年、P・セルズニックは、この考え方をより発展させ、ウェーバーのいう官僚制組織は専門化された技術の訓練の量を増大させ、確かに組織の能率は得られるが、逆に組織の部門化をもたらし、部門間の利害を増大させ、組織のコンフリクト(衝突)が発生するとする「逆機能性」があることを述べている。
確かに官僚制組織には、ある限界が存在する。ピラミッド組織そのものが主人公となり、組織メンバーに見えないところで、ほとんどのことが決定され、メンバー各人は、どこでどのように決定されているかわからないままに、あまりに多くの仕事が与えられ、かつ終わることがないといった、非人間化、非情の組織のなかにある。そのため、組織の参画メンバーに不安、葛藤、フラストレーションを与え、その結果としてメンバーは、優柔不断、理屈づけ、組織への反抗など制度悪的怠業を起こす。このような思考の放棄や怠業、要領をもって本分とする態度といったモラル低下は、能率を追求しようとした分業による専門化の弱点であることを理解しておかなくてはならない。笑い事ではない。現在も強大化した組織にこのような文化がはびこっている。それが会社を蝕んでいることを仕方なく放置している状態である。
| 前の項目 | 小売業が取り組むべき4つの組織課題 |
| 次の項目 | 動機づけ理論ブーム |
Copyright 2006 (C) Jericho Consulting Co.,Ltd.
本サイトの全ての文章、画像を無断で転載することを禁じます。