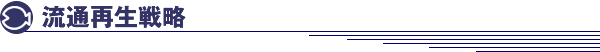第2章 小売業は人−人材育成こそ再生の条件
小売業が取り組むべき4つの組織課題
(1)管理スパンを拡大しないこと
急速な企業成長による組織管理の距離が伸びる。ナショナル・チェーンなら、北海道から九州まで、物理的距離がきわめて長くなりコントロールの困難性が増す。1店舗内でも店舗面積の拡大とともに一人当たりの管理売場面積、担当商品アイテム数が拡大する。これもコントロールを弱体化させる。一人当たりの管理の限界があるはずだ。その限界を超えてしまったら品揃えも売場の設計図も乱れてしまう。接客もままならない。ムダな人件費のカットは重要だが、管理の限界を超える要員カットは会社を潰すことになりかねない。適切な守備範囲の設定がきわめて重要だ。
(2)マネジメント訓練の徹底
急成長のあまり、充分なマネジャー訓練をすることなくマネジャーのポストを与え、マネジャーと部下とのコミュニケーションがうまくいかず、組織モラルの低下をもたらしているケースが多い。小売業は店長次第で売上が20%ほど上下する。いま小売業が早急にやらなくてはならないことは、第一線マネジャーのマネジメント力育成の教育訓練、特にコミュニケーション教育が必要である。シアーズ・ローバックを通信販売業から小売チェーンに発展させたウッド将軍は、「組織というものは重要ではあるが、頼りになるのは組織ではなく人間である」と述べている。店舗の増大とともに組織が役所式に膨張するのを嫌い、個人の能力こそ絶対であると確信し、業務のあらゆる面にわたる監督と規律を強化するとともに、無能な支配人の淘汰、有能な支配人の継続した訓練に力を入れた。つまり、徹底した人材の棚卸を行った。
(3)「組織と何かを語れる」人間の育成
幹部層から第一線のマネジャーに至るまで、「組織とは何か」を明確に理解していないと組織運営はうまく行かない。組織とは、一人で実現不可能なことを協働することによって実現するための協働体系なのであるが、単に組織図さえ作成すればことが足りるという考えが蔓延している。自分自身の部署の役割をよく理解すること、関係する他部署の役割を理解すること、相互にどのような情報を交換すれば組織効果が上がるかを常に考えること、決して他部署との壁を作らないこと、相互に現在壁となっている障害を協力して除去することなどが求められる。組織の利点と弊害は何か、組織の限界はどこにあるのか、それをカバーする運営手法はどうすべきかなど、組織の概念をしっかりと身につけ、語れるようなマネジャーが数多く存在していなくてはならない。
(4)コミュニケーション技術を磨くこと
対人折衝力といってもよい。相手方の気持ちを最高に感じとれる人間、自分の思いは後回しにして相手方は何を言いたいのかを感じとれること、自分の意見を簡潔に短く言い相手方に興味をもってもらえること、相互の対話は「相手方優先」で相互理解、相互納得の実現が目指すべきコミュニケーション、対人折衝力になる。一方的な指示・命令、聞くに耐えないだらだら発言、自分優先の推測発言、聞き出す能力不足(ヒヤリング能力)などはコミュニケーションではない。コミュニケーションの原則は「相互納得」にある。相互に納得するまで話し合いをする必要がある。そのためには「聞く能力」「話す能力」の訓練が必要となる。組織とは2人以上の協働体系であり、相互に一つの目的を理解し、それを実現するために相互の役割を理解しあわなければならない。行ってほしいことを伝達し、伝達された側にそれを理解してもらい、受容されてはじめてコミュニケーションが完結する。単に伝えたとか命令しただけのものはコミュニケーションとはいわない。ところが現実には、種々さまざまな言語が氾濫し、その言葉の解釈の議論が多く、混乱していることが多い。
| 前の項目 | 内敵と外敵 |
| 次の項目 | 学者の組織理論 |
Copyright 2006 (C) Jericho Consulting Co.,Ltd.
本サイトの全ての文章、画像を無断で転載することを禁じます。