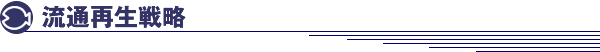第2章 小売業は人−人材育成こそ再生の条件
合理性限界論
これをH・Aサイモンは、人間は「限定された合理性」しか持たないと指摘した。彼は「人々は合理的であろうと意図するが、限られた程度でしか合理的でない。それは知識、先見、技能および時間において限界をもっているからにほかならない」と説明している。理想と現実が違ってくる原因はここに存在する。
合理的でありうる条件は、先の見通しが確実であること、選択すべき項目がすべて与えられておりかつその結果が予測されていることにあるが、現実にはそんな状況はありえない。社会はプログラム化されているのではなく、先は不確実であり、選択すべきレパートリーは多く、時間はあまりにも少ない。混沌とした世界に我々は生きている。理想郷、最高の合理性は実現が難しい。人間としての限界があるからである。
この人間の合理性の限界、言い換えると人間が不合理性をもっているかぎり、すべての人に創造的であれ、能動的であれと期待することは組織運営において混乱を招く危険がある。組織運営に当たって、心しておかなければならない人間限界論である。
| 前の項目 | 動機づけ理論ブーム |
| 次の項目 |
Copyright 2006 (C) Jericho Consulting Co.,Ltd.
本サイトの全ての文章、画像を無断で転載することを禁じます。