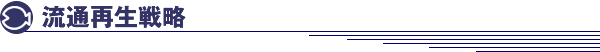スーパーマーケット経営数値構造は、大体、以下のような構造になっている。これを数値フレームという。
話を簡単にするために、スーパーマーケットの売上高を100円とする。この100円はどのように分配されているかが基本的な数値フレームとなる。
スーパーの荒利益率(スーパーマーケット業界では荒利益といい、百貨店では粗利益という)25%とする。したがって、100円のうち75円は仕入先に支払う(商品原価75円)。手元に残るのは25円。この25円からチラシ代(販促費)、人件費、電気代(水道光熱費)、家賃を払う。販売促進費を売上高100円の5%、5円とする。1円はチラシ代、1円はPOPなど装飾費、1円はポイント経費、残り2円をその他販促費として使う。残りは20円。人件費も売上高5%、5円。本社人件費も含めて5円で賄う。正社員、パート・アルバイト費が5円。残り15円になる。水道・光熱費などの管理費も売上高の5%、5円で賄う。残りは10円となる。家賃、保険、借入金返済などの資本費も売上高の5%、5円で賄う。残りは5円。これが営業利益部分になる。
しかし、リスクヘッジや投資を考えなくては経営が安定しない。
5円のうち2円を利益計上(利益率2%)。2円を商品ロス引当と考える。商品廃棄や棚卸し減耗に2%を予定する。数値上荒利益率2%の現象。つまり、帳票上最終荒利益率23%と計算される。残り1円。これを将来のための投資と考える。システムが不備ならシステム投資に当てたい。
経営数値フレームという下敷きを準備し、数値フレームに準じた予算を立案し、実績管理を徹底する。手元に残るのは100円玉のわずか5%(5円分)。ロスを5%だせば元も子もない。ロスを2%に押さえ、システム投資に1%引当するなどあらかじめ数値計画を立案する。これが経営計画である。
| 前の項目 | なぜ情報を活用できないのか |
| 次の項目 | POSデータの活用 |
Copyright 2006 (C) Jericho Consulting Co.,Ltd.
本サイトの全ての文章、画像を無断で転載することを禁じます。