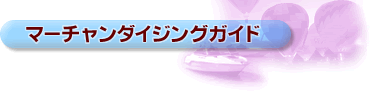|
3−1.オペ原則1つ目 商品の選定
選択は「数あるなかから選ぶ」という意味です。厳しい目、プロの目で顧客が購入するだろう商品を厳しく選ぶことです。
「自分だけの好みで品揃えする」「単に儲かりそうだからと品揃えする」「売れるだろうとデータを分析せず思いつきで品揃
えする」「おもしろそうだと品揃えする」「以前からおいているからと固定概念で品揃えする」は厳禁です。自店のお客様の
ニーズ、ウォンツをまったく考えておりません。お客様の購入データを読み取り「何を売るのか(の意志)」「どこのものを取り
扱うべきか(の意志)」「どれだけの数量をおくべきか(の意志)」「何を主力(重点)商品にするのか(の意志)」「誰に買っ
ていただきたいのか(の意志)」の考えを持たなくてはなりません。
売場にあなたの意志、作戦を反映しなければなりません。商品選定はあなたのお客様の要望を第一に考えなければなり
ません。
3−1−1.定番商品の選定
年間ほぼ一定に取り扱う基本的な商品として選定した商品を定番商品(ステープル)と言います。価格は販売期間中、
特売することなく一定の売価で販売します。売上構成比で60%、在庫構成比で55%が基準です。
3−1−2.季節商品の選定
商品には収穫期があり、収穫開始から収穫終了のサイクルがあります。お客様はその商品サイクルをよく知っています。
いちごは12月から立ち上がり終了は4月という旬のサイクルです。いちごは17世紀オランダ南蛮船が日本に伝えました。
スイカは4月末からスタート、7月が絶頂期です。さんまは7月下旬から9月末まで。かぼちゃは7月から9月、なすは7月
から100月、すだちは8月から12月です。このように季節のサイクルのある商品が季節商品(シーズン)です。 売上構
成比は30%%、在庫構成比は40%が基準です。
3−1−3.販促商品の選定
お取引先から生産や在庫の関係から特別に値下げした価格(原価)を提示され、特別価格で販売できる時、特売
価格で販売します。また、仕入れのミスや天候不順で在庫過剰が予測されたら、利益率を犠牲にして、特別価格で
在庫一掃を図ります。本来の特売商品選定です。売上構成比で10%、在庫構成比で5%が基準です。
3−2.オペ原則2つ目 在庫の適正維持
在庫と販売はトレードオフの関係です。在庫が多いと注意されると発注を控えてしまい「欠品」になり、売上がその分
減少します。本来なら売れるのに売れなかった「売上機会ロス」です。欠品してしまうと今度は欠品しないように必要
以上に仕入れてしまい過剰在庫になってしまいます。過剰在庫は、価格を下げて(売価変更)販売し在庫処分します。
価格を下げた分、利益の減少になってしまいます。単品ごとに販売データから基準在庫数量を設定しておく必要があり
ます。季節商品は、前年の52週販売データを参考にして仕入れ数量を決定してください。
3−2−1.「過剰在庫」削減オペ
過剰在庫とは在庫が多すぎることです。過剰在庫が常態化すると経営にとって大打撃になります。お金が回収できず、
資金ショートになります。店内も在庫で一杯になってしまい、陳列する場所がなく、通路にはみ出し、売場は乱れ、売
上が徐々に低下します。
「在庫過大→資金回転率低下→経営資金圧迫」になります。
3−2−2.「欠品」撲滅オペ
過少在庫になると「欠品」が起こります。過少在庫とは在庫が少なすぎることです。欠品はPOSデータで把握できません。
欠品データは取得できないので、売場での目による管理が必要です。欠品は「売上機会ロス」です。データを分析しな
い仕入れ行動もしばしば過剰在庫や過少在庫に状態を起こします。「在庫切れ→品切れ→売上機会ロス」になり売上
低下要因になります。
3−2−3.「バックルーム在庫」削減オペ
在庫は「売場在庫+バックルーム在庫」の合計です。売場在庫は「目による在庫管理」でコントロールできますが、売場
で陳列できなかった残りの商品はバックルームにダンボール入ったまま保管しています。このバックルーム在庫はコント
ロールが困難です。つぎのような工夫をして在庫管理をしましょう。
ダンボール積み上げではなくラック保管形式にします。そして「定位置管理」をし、定位置を記号化します。記号でバックル
ーム在庫を管理するようにします。これをパソコンなどで情報管理すればバックルーム在庫管理が実現します。在庫管理
工夫オペです。
3−2−4.「適正在庫」維持オペ
適正在庫を維持するために自動発注「セルワンバイワン」方式を採用します。トヨタ自動車の生産管理「ジャスト・イン・
タイム」の採用です。ジャスト・イン・タイムは下流工程で必要になった部品を上流工程に「カンバン」で部品を要求する
方式です。この方式で工程にたまってしまう部品在庫を大幅に縮小することが出来ました。これを小売業の在庫管理に
応用します。それがセルワンバイワン方式の自動発注です。
POSデータから、毎日、単品の販売数量が把握できます。毎日の販売数量を加算し、基準在庫を維持する発注点に
達したらお取引先に自動的にシステムが発注データを電子式に流します。店舗が閉まっていても深夜でもシステムが自
動的に取引先のシステムに発注データを届けるシステムです。
3−3.オペ原則3つ目 正しい陳列維持
商品をキチンときれいに順序よく並べられ、お客様が混乱を起こさず、ストレスを感じることなく、気持よく買い物できる
ように適切な陳列を維持する必要があります。これは顧客を維持する絶対原則です。
「陳列は乱れていない」「買いたいと思った商品が欠品していない」「商品が押しこみ陳列されていない」「決められた位置
以外に置かれていない」「通るのに邪魔なものが通路にはみ出していない」「山積みされていて取りにくい」「プライスカード
がきちんと付いている」「ホコリが付着していない」「見苦しくなく美しい」などが正しい陳列です。この逆が間違った陳列です。
3−3−1.陳列技術
陳列技術の基本を述べます。つぎの4項目です。
1. できるだけ多くの商品がキチンと並べられている
2. お客様に、その陳列が全部見ようと思わせるようになっている
3. お客様が近づきやすいように並べられている
4. お客様が何者にも妨げられずに手に取りやすいようになっている
どうでしょうか? 4つの原則、全部満足しているでしょうか?
3−3−1.陳列の整理整頓
何より重要なことが「整理整頓」です。口で言うのは簡単ですが、いざ実行となると大変難しいのが整理整頓です。例え
ばオフィスでの資料整理は資料の種類別にきちんと保管されていることです。整頓とは保管されている資料を「必要な時
10秒以内」に取り出せることです。10秒以内に取り出すためには整理ができていなければなりません。整理と整頓の用語
を定義しておきます。整理・整頓・清掃・清潔・しつけを「5S」ということもあります。
3−4.店内空間コントロール1つ目 「フェイス管理」の知識と実践
店内コントロール(管理)は主に、商品の配置、スペースの割り当て、棚の生産的活用、関連陳列です。この視点から、
まず、フェイス管理について述べます。つぎの4項目を常に意識します。フェイスは商品の顔、商品名が書いている面を言
います。
3−4−1.何を並べるかアイテム(品目)の決定
洋日配部門、牛乳カテゴリーに「おいしい牛乳」を冷ケースに陳列します。冷ケース(棚種別コード)やゴンドラ棚単位に
棚番号、棚段番号で管理します。どの棚の何段目に何を並べるかを決定していきます。
3−4−2.フェイス数と陳列数の決定
フェイス数とは横フェイス、縦フェイスに分けます。横フェイスとは、おいしい牛乳を横に何個(何列)並べるかです。縦フェイス
は縦に何段積み上げるかです。基本は横フェイスで管理します。陳列数はフェイス数と1フェイス当り奥行き何個置くかによ
って決まります。1フェイス当り奥行き10個、3フェイスであれば陳列数は30個になります。
3−4−3.フェイス面の決定
商品の面は「正面」「裏面」「上面」「底面」「横面」があります。正面は商品名、裏面や横面には原材料名など記載され
ています。この面のどちらをお客様側に見せるかの決定です。通常、商品名が印刷されている面を通路側に向けます。
3フェイスなら真ん中は原材料は書いてある裏面、その左右は正面にするというような決定もあります。
3−4−4.陳列の位置の決定
5段のゴンドラなら、一番下はお客様に見えないのでなかなか売れません。目の高さ以上にある上段も売れません。「ゴー
ルデンライン」があり、これはお客様の目の高さ、1メートル50センチなど、ゴールデンラインといいます。一番目につき、売れる
位置であり、この位置に売れる商品を陳列します。需要の少ない商品を売れないからといってゴールデンラインに陳列するの
は経済学的邪道です。小さな子供商品は、問題を起こすからという理由で上段に陳列するのは間違いです。子供の目の高
さに陳列します。
3−5.店内空間コントロール2つ目 陳列
陳列で重要なフェィス管理について述べましたが、店内空間管理のその他重要項目について説明しておきます。前進陳列、
関連陳列の重要性とビジュアル陳列への注目です。
3−5−1.前進陳列を意識する
ゴンドラ、棚陳列商品の前出しを徹底する行動です。お店が開店して、買い物が始まると、棚から商品が消えていきます。
売れる商品ほど前面の商品がなくなり、奥にしか商品がありません。通路を早足で通るお客様には棚奥の商品は見えません。
つまり見えない商品は「欠品」と同じことです。この問題を解決する最大の方法が前出しです。
全従業員、担当にかかわらず、通路を通る時、前出しする習慣を身に付ける必要があります。スーパーマーケットの最も基本
的な動作です。
3−5−2.関連陳列を意識する
関連の強い商品同士を関連付けて陳列し「衝動買い」を刺激する陳列です。常識とは違った陳列にお客様は目を向けるよう
になります。
お客様の食事の料理支援にもなります。日本では来店されるお客様の80%近くが今晩のメニューを決めずに来店されていると
いうアンケート調査があります。今晩の料理をイメージさせ、買い忘れのないように陳列します。さんまのシーズン、生さんまの前に
大根を陳列する。猛暑、食欲不振、絹豆腐と「きざみネギ」を関連して陳列する。関連陳列することによって販売点数をアップ
することができます。
3−5−2−1.「併買率」という数値
同時に購入される商品の比率です。たとえば、さんまの購入者100人、その100人で大根を同時に購入していた人が30人
だったとすると併買率は30%%です。関連購買分析(バスケット分析とも表現する)で併買率が高い商品は関連して購買され
ている商品ということになります。
3−5−2−2.「リフト値」という数値
支持率と併買率の相関関係で関連が高いか低いかを判定する非常に参考になる統計数値です。支持率とは来店客数
1000人、その商品購入者100人なら支持率は10%%です。
リフト値とは、併買率を支持率で除算した数値です。併買率が支持率より1以上高いと関連があると判定します。この数値
が高いほど関連して購買される傾向があります。
クラフトモッツァレラの支持率0.1%でした。クラフトモッツァレラ購入者がサントリー赤ワインを同時購入した併買率が0.5%でした。
リフト値は5です。(ワイン併買率0.5÷クラフトモッツァレラ支持率0.1)
3−5−3.ビジュアルマーチャンダイジング VMD
ビジュアルマーチャンダイジングは人間の感覚に訴求する陳列です。「清潔だ」「綺麗ね」「美しい」「感じがいいね」「面白い」
「ユニークね」とか「視覚」に訴求する陳列手法です。
ビジュアルマーチャンダイジングは「VMD=VP+PP+IP」で構成しています。
VP(ビジュアルプレゼンテーション)は、店頭やコーナー部分で売場全体のイメージを作るディスプレーの表現です。
PP(ポイントプレゼンテーション)は、店内の柱周りや壁面で商品を引き立てる演出をするディスプレーの表現です。
IP(アイテムプレゼンテーション)は、陳列している商品購入意思決定を促進する陳列演出の表現です。
VMDの実践にも取り組み、お客様が気分よく買い物できるような売場を実現しましよう。
|