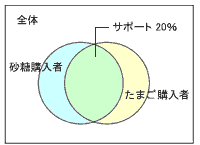| カナ | 用語 | 解説 |
| サイ | 再販商品 | メーカーが卸売価格や小売価格を維持するためにとる再販売価格維持制度に該当する商品。指定商品と法定商品があり、前者は公正取引委員会の指定を受けたもので、化粧品や医薬品などが該当する。後者は「独占禁止法」の適用除外扱いとなっているもので、主に出版物などの著作物が該当する。 |
| 再販売価格 | 再販売価格維持契約における再販売商品の指示価格。価格の決め方には、定価より指示価格を低く指定し再販売価格に幅を持たせる値幅再販、定価のみを指示する確定再叛、最低価格のみを指示するもの、などがある。 | |
| 再販売価格維持制度 | 製造業者または卸業者が、その商品の販売価格を、以後の流通段階において守らせるように統制すること。これが法的に許されるには公正取引委員会の指示にもとづいた再販売価格維持契約が必要であり、この条件が満たされないまま再販売価格維持政策をとると、いわゆるヤミ再販として、不当な拘束条件付取引となり、「独占禁止法」に違反することになる。 | |
| 債務不履行 | 売買契約における売主側、あるいは委託請負契約における請負側が、契約によって生じた債務(品物の引渡しとか工事完了など)を履行しないことをいう。債務不履行責任としては、履行期までの間に滅失・穀拐したなど履行不能となるケース、受注側(債務者)の帰責事由で履行遅滞となるケース、履行はされたが不完全履行であるケースなどに区分される。訪問販売や通信販売など販売方法が多様化してくると、このようなトラブルが発生しがちになるので、契約時に条件を明示することが大変重要となってくる。 | |
| ザイ | 在庫 | 企業が製品や半製品あるいは原材料などの形で保有する資産。需要が活発で出入りが頻繁なものをランニング・ストックといい、倉庫に入ったまま売れる見込みのないものをデッド・ストック(死蔵在庫)という。このデッド・ストックを出さないためには、日常の在庫管理を徹底しか商品の売行き状況の把握につとめることが重要である。 |
| 在庫回転率 | 使用高あるいは売上高を在庫高で割ったもので、一定期間内において在庫が何回回転したかを示す数値。在庫高は月末現在在庫とか、年度末現在在庫、あるいは月初・月末の在庫高の平均など、回転率の用途によって種々の在庫数値が使われる。在庫回転率年間12回なら、在庫が12回転していることを意味する。 | |
| 在庫管理 | 物流体系全体を通して在庫の配分は物流システムの基本である。サービス率を必要な水準に保ち、しかも必要最低限の在庫を各拠点で保有することが大切であり、これを実現する手段が在庫管理手段である。具体的には庫量を正確に把握すること、在庫切れあるいは過剰在庫をなくし、適正在庫を確保すること、在庫品の破損や減耗をなくし、品質保持すること、などがあげられる。在庫管理は第二の収益源ともいわれており、在庫管理の合理化・効率化に各企業とも大きな力を注いでいる。特に小売業において在庫管理が不徹底であると、品切れを発生させ、売上機会ロスになり、顧客離れを発生させるなど、致命的ともいえる問題を発生させるもととなる。在庫管理には発注時を定めて行うものと、発注点を定めて行うものがあるが、いずれにせよ安全在庫量、発注量の決定が科学的に行われねばならない。 | |
| 在庫調整 | その時々の経済動向や需要動向にあわせて在庫量を増減して調整すること。景気が落ち込んでくると在庫は増大しがちになるが、それを抑え、適正水準まで減少させることを一般的に在庫調整という場合が多い。具体的な手段としては、生産制限をしたり、安売りによって在庫処分したりするのが通例である。 | |
| 在庫日数 | 手持ちの在庫商品が何日分の販売額に相当するかをいい、適正在庫を知る指標となる。予定の商品回転率や売上高を勘案しながら、適正な在庫日数にコントロールする必要がある。つぎの公式で計算する。 手持ち在庫日数=在庫高(売価)÷1日平均売上高 |
|
| サエ | 差益高 | ある商品が販売された時点で得られた利益のことで、もっとも基本的な経営計数である。売上高−売上原価(仕入高)で求められ、粗利益高とも荒利益高ともいう。差益高は個々の商品によって異なり、仕入時期と販売時期との間には一般的にずれがあるので、全体としての差益高管理には常に留意する必要がある。差益高が売上高に占める比率を差益率と呼び、パーセントで表わす。 |
| サキ |
サーキュレーション 【circulation】 |
一般に媒体価値の評価尺度として使われる言葉。広告媒体の伝達範囲のこと。新聞や雑誌は発行部数または販売部数、テレビ・ラジオは視聴されているテレビ・ラジオのセット数もしくは常に視聴・聴取される一定地域内のテレビ・ラジオのセット数によって測定される。屋外広告は、その広告を見る機会を持っている歩行者・車両利用者の数、交通広告では車内・駅の乗客数・乗降客数、映画舘・劇場広告では入場者数がサーキュレーションと呼ばれる。通常、新聞折込数を言う場合が多い。 |
| ザツ | 雑誌広告 | 雑誌の紙面を利用した広告。雑誌は季刊、月刊、週刊など一定の間隔で発行される定期刊行物の総称。雑誌広告の特徴は、新聞が一部の全国紙を除くと殆どが地方媒体なのに対し全国媒体であること、対象がはっきりしていること、カラーで情報提供ができることなどがあげられる。特に最近では、特定のライフスタイルの読者に絞った雑誌が相次いで創刊されており、顧客層を意識した広告展開が可能になる。 |
| サビ | サービス | サービスは、それ自体価値を有するものとして販売されるものと、財貨の販売にともなって、それに付帯して提供されるものがある。前者の場合、映画、ゴルフ、ボーリング、理髪、ホテルなどがあげられる。後者の場合、放送、装飾、催物のサービス、用途説明のサービス、配達、返品、交換、修理などがあげられる。つまり、購入者あるいは使用者に何らかの用役を提供するか、あるいは顧客への財貨の販売にあわせて満足感を与えようとするものがサービスの本質である。 |
| サービス化 | モノに対するサービス、ハードに対するソフトという関係で、その比重がモノからサービスへ、あるいはハードからソフトヘ移ることをいう。経済のサービス化、家計のサービス化などといった表現で使われることが多い。サービス化の背景には、基本的な生活ニーズが充足されるにしたがって、生活者の要求が高度化し、個性化するためであり(マズローの欲求5段階説)、それに伴って、サービスニーズの比率が高まる。産業構造もサービス業を中心とした第三次産業の比重が高まり、家計も財貨への支出から教養・レジャー支出などのサービス関係支出が増大する。 | |
| サービス業 | 無形財の販売業のこと。内容は多種多様であり、特に最近では新たなサービス業の出現およびその成長が著しい。情報提供をめざした情報サービス業、家事や雑事一般を代行する代行サービス業などがあり、サービス業の発生とその成長は、時代を先取りし、時代を映す鏡であるといえる。サービス業隆盛の背景には、家計のサービス化のことばに代表されるように、教養・レジャー費などのサービス支出の増大や主婦就業率の上昇による家事労働の外注化がある。 | |
| サービス経済化 | 産業構造においてサービス業の比率が高くなっていくこと。経済社会が高度化、成熟化すると、第三次産業の分野が拡大することはよく知られているが、サービス経済化もその延長線上にある。最初は卸・小売業、金融・保険業、運輸・通信業、飲食業という伝統的なサービス産業が、生産額のシェアを高め就業者を拡大し、続いて教育、医療、家事、公共レジャー、情報などの分野で、新しいサービス産業が誕生してく。わが国のサービス経済化もかなり進んできており、販売の面からみれば、モノだけの販売ではなく、販売時点でサービスをどのように付け加え、付加価値を高めるかが重要なポイントとなってきている。 | |
| サービス商品 | 百貨店やスーパーマーケットなどが新たに拡大しようとしているサービスを中心とした商品分野。消費者のモノ離れ傾向、生活のサービス化が大きな流れとなっているために急速に発達している。クレジットカード、金融、保険、旅行、教養講座、増・改築、宅配、宴会、劇場のチケットなど、さまざまな商品開発がみられる。サービス機能を強化することは、大型小売業にとっては顧客の動員、販売促進の機能として重視されていたが、それが収益を生む商品としても定着してきている。セブンイレブン、ローソンなどコンビニエンスストアが、公共料金の振り込みサービスやインターネットビジネスの集金と配達のサービスをつぎつぎに開発しているのは生活者への総合的なサービス提供の現れである。 | |
|
サービス・マーク 【service mark】 |
銀行やホテル、運送業など、サービスを提供することを営業内容とする業者のマークのこと。法律上は標章ではあるが商標ではないため、「商標法」による保証はないが、「不正競争防止法」の適用を設けて保護される。 | |
|
サービス・ 【service merchandising】 |
卸売業が、商品の保管・流通という基本機能に加え、小売業に対して新しく提供するサービスをいう。その内容は、店内インテリア、品揃え、販促企画・販売データの提供、陳列棚の管理、値付け、在庫管理)、配送など、小売店経営の大部分のサービスを総合的に提供するものである。サービスは原則として有料。商品別に専門化しメーカー色の強いわが国の卸売業では障害も多いが、″卸売業の生き残る道″といった意見も多い。リテイル・サポート・ビジネスという言葉で言われることが多くなった。 | |
| サービス率 | 在庫管理における品切れ防止を示す指標。品切れ率が高い場合、サービス率は低い。品切れ率が低い場合、サービス率は高い。品切れ率がゼロならサービス率は100%となる。品切れは売上機会を失うだけでなく、顧客の信用を失う第一歩であり、品切れを発生させない十分な発注管理と在庫管理が必要である。品切れ率はつぎのような三種類のものがよく使われる。 ・サービス率=(1−品切れをおこした顧客数/総顧客数)×100(%) ・サービス率=(1−品切れ数量/総需要数量)×100(%) ・サービス率=(1−品切れ金額/総需要金額)×100(%) |
|
| サブ |
サブ・クエスチョン 【sub-question】 |
調査対象者の一部の人にだけ答えてもらう質問。たとえば「あなたは毛糸編物をしたことがありますか」という質問に「はい」と答えた人に、いつ、どんな毛糸を使って、何を編みましたか、というように詳しく聞いてゆく。「いいえ」の人は、このサブ・クエスチョンは飛ばすことになる。市場調査などで消費者意識をよりきめ細かく把握するためには、特定の反応を示した消費者に追加質問をする必要がある。サブ・クエスチョンの入った質問紙は、質問の流れを分りやすくし、誰がどの質問に答えればよいかが一目瞭然になるように配慮されなければならない。 |
| サブ通路 | 店内で主要な売場に誘導するための通路を主通路または、メイン通路というが、それに対してサブに当たる通路をいう。店内をくまなく歩いて買物をして欲しいのが店側の理想であるが、どうしても客が集中しがちな場所があり、逆に、客が立寄りにくい売場も出てくる。その調整のために、サブ通路を上手に組合せて意外性を持たせた通路、たとえば三角型に通路をつけたりして、どこの通路も売場に向かうようにすることが可能となる。 | |
| サプ |
サプライチェーン・マネジメント 【SCM】 |
商品の企画、部材の手配から始まり、製造・販売にいたるまでの商品と情報の流れがサプライチェーンである。サプライチェーンのなかで、企業や組織の壁を超え、ひとつのビジネス・プロセスとして情報や資源を共有し、サプライチェーンの全体最適を達成しようとする管理手法である。 |
| サプライチェーン・ マネジメント・管理ソフト・ パッケージ |
サプライチェーン内の業務を効率的に処理することを目的として開発されたパッケージ・ソフトウェア。本来、社内業務のみだけでなく、パートナー企業との情報共有により企業の壁を超えた業務を取り扱うが、現在は企業内の適用分野に使われているのが多い。需要予測、生産計画、製造ライン計画、在庫計画、供給計画、物流計画、納期回答などの管理ソフト・パッケージがある。 | |
| サベ | 差別化政策 | 商品やサービス、店舗イメージなどで競合相手との違いを強調し、競合条件を優位にするマーケティング戦略。差別化政策は、価格や製品機能などの同質競争を避け、商品デザインやサービスなど、競合相手と異質な優位性を訴求することによって、新しい需要を開拓し、マーケット・シェアを拡大することを目的とする。差別化の方法は、製品差別化、サービス差別化、イメージ差別化など各種ある。 |
| 差別対価 | 正当な理由なしに、地域または相手方により、差別的な対価で物質、資金その他の経済上の利益を供給し、または供給を受けること。「独占禁止法」で不公正な取引方法として指定し、禁止している。 | |
| サポ |
サポート 【support】 |
データマイニングの際の、相関分析の指標のひとつで、ある関連購買における支持率を表す。たとえば砂糖について卵の関連購買でサポートが20%の場合、砂糖と卵を一緒に購入する顧客が顧客全体の20%という意味である。*リフト値、コンフィデンスをご参照ください。 |
| サン | 三条申請 | 「大店法」(「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調優に関する法律」)第三条の規定による大型小売店の出店または増床の際、建物設置者の届出義務をいう。具体的には、出店予定の店舗面積が500平方メートルを超えるもの(増床によって全体の店舗面積が500平方メートルを超えるものを含む)は届出が必要であり、このうち1500平方メートル以上(都の特別区および政令指定都市では3500平方メートル以上)の場合は通商産業大臣、その他の場合には都道府県知事に届出をしなければならない。その店舗が周辺の小売業者に相当程度の影響を及ぼすことが予想される場合には、通商産業大臣または都道府県知事は、大規模小売店舗審議会に諮問し、開店日、売場面積、閉店時刻、休業日数について答申を受け、調整することになっている。審議会は答申にあたり、商工会議所または商工会の意見を聞いて、商業活動調整協議会に諮問したうえで審議会に答申する。 |
| 産地直送 | 農産物を対象に、消費者団体や小売業者が卸売業者などの既存の流通経路を通さずに生産者と直接取引をするもので、産地直取引ともいう。新鮮で安価な農産物の販売あるいは購入を目的としたものであり、商品の高品質と価格の低廉さが同時に達成されることになる。 | |
| 参入障壁 | 特定の市場に新たな企業が乗り出す時に、その参入を困難にさせる様々な要因のこと。この参入障壁は、利益の規模が大きく、既存企業の製品差別化の程度が高く、しかも、販売ネットワークづくりに特別な条件が必要となるような産業や市場ほど高くなる。産業でみると、自動車や家庭電化製品などの耐久消費財産業などがこれらの条件に適合しており、それだけ参入障壁の高い産業、いいかえれば新たな企業が参入しにくい産業であるといえる。販売という分野は比較的参入がしやすい分野であり、新しい販売方法を開発した企業が絶えず参入してきている。 | |
|
サンプリング 【sampling】 |
市場調査などで母集団からサンプル(標本)を抽出することをいう。ある大きな集団(母集団)の特性などを調べる場合、その集団のすべてを調べるのではあまりにも費用と時間がかかってしまう。そこでその母集団から標本を抽出し、その標本を調べることによって母集団の特性を推測する方法が有効となる。来店客の特性を把握するための来店客調査などでも、全来店者を対象とするのではなく、一定数の来店客を調査して全体の特性をつかむ方法が用いられている。この場合でも、来店客のサンプリングが行なわれている。コンピュータ上でデータマイニングを利用し、意味のある事象を発見するために膨大な詳細データからランダムにデータをサンプリングして分析する。この場合のサンプリングも同じ意味である。 |