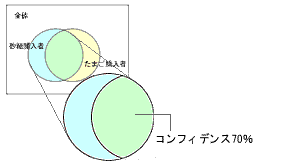| カナ | 用語 | 解説 |
| コウ | 高圧的販売 | とにかく売りさえすればよいといった売手側の論理によって、お客の要望や迷惑をあまり考えずに商品を押しつけ、お客に後味の悪い印象を与えてしまう商法のこと。このような販売は、一時的に売上高をあげることができても、結局はお客の信頼を失い長期的に安定した成績をあげることはできない。逆にお客の立場に立って、商品やサービスの購入により満足感を得てもらうという視点の販売を、低圧的販売という。 |
|
広告カバレッジ 【advertising coverage】 |
送り手側が出した広告を受けとめることができる地域や、そこの世帯数などをいう。広告媒体の到着可能地域ともいう。テレビやラジオであれば、受信地域=サービスエリアである。新聞・雑誌などの印刷媒体は、配布地域や発行部数をもって、広告がカバレッジされた、というように使う。理想的には、広告カバレッジと販売地域が一致していることが望ましいが、現実には、媒体の特性によって差が出てしまうのが実体である。 | |
| 広告企業 | 一般には広告代理店(広告エージェントまたはアドバタイジング・エージェント)と呼ばれており、広告主(たとえば商品販売企業)と広告媒体社(新聞社や雑誌発行企業)との間にあって、媒体のスペースや時間を販売していた企業のこと。近年、広告主に対するマーケティング・サービスが重視されるようになり、また、自社独自のダイレクト・マーケティングを展開する企業が現われ、広告企業と呼ばれるようになってきている。広告企業となることによって、広告代理店は、企業の販売のためのよきアドバイザーとなり、パートナーとなる。 | |
| 広告効果測定 | 広告の目的がどの程度達成されたか測定すること。広告の効果には、意識してくれる、態度を変えてくれる、買ってくれる、の三段階がある。この三段階のうち、もっとも正確に潮定できるのが意識効果で、購入したかどうかの購買効果となると明確ではない。しかし、広告主側にしてみれば、その購買効果を最も強く希望し、意識効果はあまり必要としていない。このことから、現在では態度を変えてくれる効果を測定することが広告効果測定のねらいとなっている。 | |
| 広告コンセプト | 広告する場合の基本的な「考えかた」「主張」をさす。商品広告の場合であれば、商品のセールスポイントは何か、何を最も重点的に売り出すか、生活シーンのどこで利用してほしいか、などコンセプト(概念)を伝える。企業姿勢紹介広告なら、何の会社で、社会的貢献は何か、目指している企業姿勢などマットも伝えたい企業理念を伝える。広告の要点といってよい。 | |
| 広告審査機構 | 広告主が自ら広告倫理を掲げて、消費者に真実を伝えるチェック機関。昭和40年代に入って起こった消費者意識の向上にともない、広告倫理への関心が強まったことが、発足のきっかけ。すでに米国には、BBB(ベター・ビジネス・ビューロー)という機構があり、その活動をもとにして、昭和49年10月、広告主の自主規制機構として「社団法人日本広告審査機構(JARO)」が誕生、広告環境浄化のための自主活動を行なっている。 | |
| 広告訴求 | 広告などのメッセージを伝えようとする相手を訴求対象という。また、訴求対象に伝えるべき商品のセールスポイントや、情報の重要点を訴求ポイントという。 | |
| 広告ターゲット | ターゲットとは「的」の意味。標的ともいう。広告したい相手、買ってもらいたい対象、買うであろう対象のこと。高度成長期は、不特定多数、マス、大衆というように「誰でも」というあいまいな表現でもよかったが、社会・経済の成熟化にともない個性化が進展し、消費者のニーズ・ウォンツは多様化し、分散化してきた。分衆の時代、個の時代などと表現される時代である。したがって、すべてを対照するのではなくある塊・グループを的(ターゲット)として商品広告や企業広告をするようになってきている。 | |
| 広告露出 | 新聞、雑誌などに広告を掲載することやTV、ラジオに広告を流すことを広告露出という。また、その頻度・量をさして広告露出量という。 | |
| 公正取引委員会 | 「独占禁止法」の目的を達成するために設置された行政機関。「独占禁止法」の目的は、私的独占の禁止、不当な取引制限の禁止、不公正な取引力浅の禁止という三つの中心的手段を通じて、公正かつ自由な競争を促進し、一般消費者の利益を確保するとともに国民経済の民主的で健全な発達を促進することである。行政組織上は総理府の外局となり、その職権行使については独立性が与えられている。権限としては行政的権限のほか、再販商品の指定などの準立法的権限と審判などの準司法的権限を有している。 | |
| 公正マーク | 各業界の公正取引協議会が、自主的に認定基準を設定して合格したものにつけるマークで、公正取引委員会が承認したもの。例としては、観光土産品の認定証、レモン果汁入り合成レモンの合格証、牛乳・加工乳・乳欧料の公正マークなどがある。 | |
| 行動科学 | 人間行動の一般的法則性を明らかにしようとするため人間行動を諸側面から研究する社会学、心理学、社会心理学、文化人類学、生態学などの諸科学をいう。行動科学、とくに心理学と社会学は、マーケティングの理論や実務に非常に貢献してきている。行動科学の強みは、経済学が無視してきていた消費者行動の理由に対する説明にある。 | |
| 購買意向調査 | 人々はいつでも将来に対する見通しを多かれ少なかれもっており、その見通しの上に立って行動している。購買意向調査は、このような人々の将来に対する見通しのうちで、購買行動に関する側面を調査しようとするもの。購買意向調査の結果は、自社の販売予測、販売計画の資料として利用できる。 | |
| 購買行動モデル | 購買者行動もデル、消費者行動モデルと同義と考えてよい。購買モデルは、消費者の購買行動に関するモデルの総称であって、その中にはきわめて多数のモデルが含まれるが、大別すれば消費者購買行動の特定の側面、たとえば購買心理過程に注目し、その側面についてモデル構築した個別的・部分的モデルというカテゴリーと、消費者の購買行動の全体構造を明らかにすることを目指した総合的・全体的なモデルというカテゴリ−に二分することができる。 | |
| 購買時点広告 | 通常、広告といえば4媒体(テレビ、ラジオ、新聞、雑誌)を通じる広域的なマス・コミュニケーション、またはDM、折り込み、ポスター、サインボードなど、文字通り「広く告げる」形態のものをさす。消費者はこれらの広域的なコミュニケーションを受けるが、最終購買段階である小売店頭に置いてさらに究極的コミュニケーションによって大きく購買行動が影響される。小売店販売員による口答のコミュニケーション、陳列位置でのパネル、スタンド、ショーカード、ポスターなどによって緻密な情報提供が購買に影響を与える。この種の購買時点・購買位置でのコミュニケーションを購買時点広告(POP)という。 | |
| 購買動機 | 顧客が商品の購入やサービスの利用を思い立つ動機。商品やサービスを購買してみようという気持を起こさせる要因。マーケティング戦略において、この購買動機の把握はきわめて重要な意味をもっている。製品開発ならどのような製品機能を顧客が求めているかを把握することによって新製品開発に生かすことができる。広告なら顧客が求めている生活シーンや機能の訴求で購買促進することができる。小売業なら陳列商品の購買決定への影響を測定することによって店頭陳列の方向づけに役立てることができる。一般的に、購買動機は価格(経済性)、合理性、安全性、レジャー性、趣味・嗜好性、社会行事、記念日、新機能、アフターサービスなどが購買動機につながる。 | |
| 広報 | 企業や団体が、自分の組織体をよく理解してもらい繁栄させるために行う活動。広告が、直接的であるのに対し、間接的な面をもつのが特徴であるパブリック・リレーションからの訳で、PRともいう。対象は、自社内をはじめ、取引先、マスコミ、地域、行政、一般人にまで及ぶため、その対象ごとに細かく行なわないと効果が発揮できない。 | |
| 小売吸引力の法則 | 小売重力の法則とか小売引力の法則とも呼ばれている。W.J.ライリーとP.D.コンパースの著作で有名。1927年ライリーによって行われた小売取引の分析にその起源を発し、コンパースの業績は、ライリーの研究成果をいっそう完全なものとし、また都市間の小売取引運動について新しい測定法の展開に焦点がしぼられている。ライリー及びコンパースによってなされた研究は、小売吸引力の法則と呼ばれる6つの公式の展開に到達した。ライリーは「2つの都市は、ほぼ都市の人口に正比例し、これら2都市からその中間都市への距離の2乗に、逆比例して、境界点の近くにある中間都市からの小売取引料を吸引する」と述べた。このライリーの法則の考え方がニュートンの万有引力の法則に類似しているところから小売引力の法則、あるいは引力モデルといわれている。引力モデルには、このほかコンパースの法則、ハフ・モデルといわれるものがある。 | |
| 小売価格 | 最終ユーザに販売する価格。小売価格は、競争上の問題や、購入促進のための刺激策、企業利益の確保という3つの側面から考慮されなければならない。とくに、最終ユーザに購入されてはじめて利益は生まれるのであり、最終ユーザの値頃感を重視した価格の設定が重要となってくる。980円、9800円といったような端数価格、日替り価格、割引価格といったような、価格についての柔軟性を持つことが、小売価格ではよく使われる。 | |
| 小売業者 | 商品を最終消費者に販売するという流通の最も川下に位置している販売業者。メーカー主導のマーケティングが主流をなしていた高度成長時代における小売業は、メーカーが開発し問屋が配送してくる商品をただ店頭に並べておくという受身的な業態であった。しかし、成熟市場時代になった今日では、最終消費者との接点に位置する小売業の役割は極めて大きくなっている。消費者の購買代理人として消費者の求めている商品を仕入れ、店頭において生活情報を提供するといった小売業独自のマーケティング活動が重要となっている。小売業はその販売あるいは設備の規模から大規模小売業と中小規模小売業に分けられ、前者には百貨店、チェーン・ストア、ゼネラル・マーチャンダイジング・ストア(GMS)、大規模スーパー・マーケットなどが含まれる。後者は非多店舗経営の専門店、近隣点、いわゆる商店などが含まれる。 | |
| 小売二法 | 昭和48年に同時に成立した「中小小売商業振興法」と「大規模小売市場法」の2つをこう呼んでいる。「中小小売商業振興法」は、中小小売業の育成と競争力を強化するための具体的な施策を決めたもので、「大規模小売市場法」はあらゆる形態の大規模市場を抑制することによって地域の小売商業活動を保護しようとするものである。昭和40年代の末以降、流通業界では、競争秩序の整備と近代化の推進が重要な課題であることを背景として成立したものである。 | |
|
小売の輪 【wheel of retailing】 |
米国ハーバード・ビジネス・スクールの名誉教授M.P.マクネアが、1957年、『マーケティングの諸問題』のなかで「小売の輪」として、小売形態の変遷をライフサイクルの視点から説明した理論。その著書でつぎのように書いている。「競争の激しいわが国の高水準経済において、流通部門で何が起きているのか。現在生じている小売形態の変化の原動力は何なのか。私が思うには、米国の流通には多かれ少なかれ、明白なサイクルが存在するようである。サイクルは大胆で斬新なコンセプト、つまり革新で始まる。誰かがいままでにない斬新なすばらしいアイデアを思いつく。ジョウン・ワナメーカー、ジョージ・ハートフォード、フランク・ウールワース、W.T.グランド、ミッチェル・カレン、それにユージン・ファーカウフといった人々である。このような革新者は新しい種類の流通企業のアイデアをもっている。 当初、革新者に対する評価は低く、嘲笑の的となり、軽蔑され、正当ではない異端児として非難される。しかし革新者はその革新固有の低い営業費によって可能となった価格訴求をベースに大衆を引きつける。後になるにつれて次第に革新者は格上げを行い、より高品質の商品を取り扱い、店舗の外観と店格を高め、より高い社会的地位を得ていく。そのころ、その小売形態は、成熟段階にはいる。建物を含む物理的施設が巨大化し、店舗の設備と陳列は洗練されたものとなり、より大々的な販売促進努力が展開される。成熟段階はまもなく過大資本化、保守化の進行、投下資本利益率の低下、ひいては抵抗力の弱体化を伴うようになる。」つまり、価格訴求の革新者が現れ、その成功が品揃え訴求に進展、そしてサービス訴求、つぎの新たな価格訴求者というように小売業態が輪のようにまわることを唱えたもの。 | |
|
高齢化社会 【aging society】 |
人口構造に占める中高齢者の比率が年々高まる社会。わが国では高齢化のテンポが短期間で、欧米諸国では一世紀以上も費やした経過をわずか半世紀足らずで到達するものと予測されている。このような急激な変化は、市場にも大きな影響を与えており、シルバーマーケット、熟年市場、アダルトマーケットなどと呼ばれながら、急速に市場は拡大している。高齢化社会では人々は将来展望を望むので、販売戦略上も十分な配慮が必要である。1999年、わが国65歳以上の人口は2117万人、人口に占める割合は16.7%となっている。 | |
|
高齢社会 【aged society】 |
高齢者の構成比が一定の高い比率に到達した、高齢者のウェイトが大きい社会をさす。高齢社会にはまだ明確な定義はないが、たとえば国連統計で65歳以上の人口比率が7%以上の社会と定義しており、すでにわが国は高齢社会ということになる。 | |
| ゴウ | 合理化の原則 | つぎの5つの原則がある。(1)標準化(Standalization)、(2)単純化(Simplification)、(3)特殊化(Specialization)、(4)システム化(System)、(5)大量化(Scale)。このなかで特に重要な原則は標準化である。標準化されないと、さまざまなムダが発生する。標準化とは、品質・形状・寸法を標準にしたがって統一すること。これに結って互換性は高まる。 |
| コキ |
顧客カード 【customer card】 |
顧客カードは、大きくはクレジットカードとIDカード(個人識別カード:主にポイントカード)に分けられる。前者はキャッシュレス(決済)カードとしての色が濃い。後者は顧客を識別し、顧客の購買履歴データを獲得し、その顧客のデータを分析し、顧客との関係を強化するマーケティング上の目的で発行することが基本。クレジットカードは信用の供与であり、氏名、住所、電話番号をはじめ、家族構成、年収、職業、勤務先、勤務先電話番号などの記入が必須条件になる。IDカードは氏名、電話番号、住所が基本。企業によっては性別、生年月日、eメールアドレスなど記入するように設計している。 |
| 顧客管理 | お得意さま管理ともいう。一度、商品またはサービスを買ってくれたお客にさらに購買を促すために行うお客様との関係を管理する。データーベース・マーケティング、リレーションシップ・マーケティング、CRM(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント)、ワン・トゥ・ワン・マーケティングとさまざまな言葉で必要性をいわれるようになった。お得意さまを育成し、ロイヤルティを高め、顧客離れを防止し、継続購入客を増やし、お得意さま一人当たりの購買金額を高めて売上を安定的に確保していこうとするマーケティング手法である。 | |
| 顧客情報 | 顧客情報は顧客属性情報(基本情報、静態情報ともいう)と購買取引データ(動態情報)に大きく分かれる。この顧客基本情報と購買データを管理して顧客のニーズや購買貢献度によって顧客一人ひとりよりきめ細かなアプローチ、訴求を行っていくために顧客情報が必要になる。 | |
| 顧客組織化 | 小売業、サービス業などの、一般大衆を対象としている企業で、顧客対策の一環として顧客を組織化すること。顧客組織化は、次のような効用をもたらす。安定した顧客集団をつくる、継続した購入が期待できる、組織客をもとに新規顧客を開発する、情報収集を行う。 | |
| 顧客データベース | カード発行顧客の基本属性データ、購買データを保管しておくコンピュータソフトウェア。顧客ひとりずつ顧客番号・カード番号・氏名・住所・電話番号・郵便番号・生年月日・性別などの基本属性をデータベース化する。さらにその顧客の購入年月日・購入店舗・購入売場・購入商品分類・購入商品名・購入数料・購入金額・販売担当者などの取引データをコンピュータのデータベースに保管する。これらのデータを分析し、顧客をグループ化し、あるいは個人を抽出して顧客に営業活動を行うためのツール(道具)が顧客データベースである。 | |
| コク |
国勢調査 【census】 |
わが国の人口の状況を明らかにするため、大正9年以来、5年ごとに行なわれている調査。最新の国勢調査は平成7年(1995年)、したがって平成12年(2000年)10月、国勢調査年になる。調査内容は、性別、年齢、配偶関係、学歴、住所移動、就業状況、利用交通手段、世帯の種類、住居などについて行う。調査結果の公表は、速報、抽出集計などで、全国編、都道府県編、人口移動編など、膨大な資料として逐次発表される。 |
| 国民生活センター | 昭和45年に制定された「国民生活センター法」にもとづいて、それまでの国民生活研究所を改組して設立された特殊法人。その目的は、消費者行政拡充ということであり、具体的な活動内容は消費者問題に関する調査研究、苦情処理、商品テスト、消費者への情報提供、消費者危害情報の収集などのほか、各種教育研修などを行なっている。地方公共団体が設置している消費生活センターと連携し、またその中心的役割を果たしている。 | |
| 国民生活白書 | 毎年2月に経済企画庁から発表される国民生活に関する調査。通常、「生活白書」と呼ばれ、昭和31年に「国民生活変貌の実態」と題する白書を出して以来、消費財やサービスの需要動向、収入、生活意識など、多くの調査を活用しながら、国民生活の実態を詳細に分析している。これは、マーケティング・データとしても利用機会の多い。 | |
| コグ | 小口仕入 | 販売量や手持在庫量の実情にあわせて、一回の仕入量を必要最小限にとどめて頻繁に仕入れる方式。このメリットとしては、保管スペースが少なくてすむ、最小在庫の適正在庫を保つことができる、商品回転率を高めることができる、などがあげられる。反面、発注コスト、運送コスト、陳列コストが高くなる。また大量仕入(スケールメリット)という取引上の利点を活かすことができず、仕入原価が高くなる可能性がある。 |
| コジ |
個人面接法 【personal interview】 |
質問調査法のひとつで、調査者が調査対象者に対し1対1で面接し、質問することによってデータを収集していく方法。市場調査や世論調査で最もよく用いられる方法である。この方法のメリットとしては、調査対象者を確実にとらえられること、かなりむずかしい調査でも調査員を訓練しさえすれば可能であること、回収率が比較的よいことなど。デメリットとして調査員の主観が入りやすいこと、調査員の訓練、管理が大変であること、相当な時間・労力、費用が必要なことなど。 |
| ゴジ | 五条申請 | 「大規模小売店舗法」第五条の規定による開店の届出義務のことをいう。大規模小売店舗内で営業しようとする小売業者は、開店(予定)の5か月前までに、開店日、売場面積、開店・閉店時間、休業日などを届け出なくてはならない。届出先は、第一種大規模小売店舗(都の特別区および政令指定都市では店舗面積が2000平方メートル以上、その他は1500平方メートル以上)の場合は通商産業大臣、第二種大規模小売店舗(同500平方メートル以上)の場合は都道府県知事である。これを受けて、届出に係る大規模店の事業活動が周辺の中小小売活動に影響を及ぼすかどうかを審議会および商調協で審議して、調整する。5か月前までに届出をすることになっているのは、この調整に長期間を要するためである。 |
| コス |
コスト・テーブル 【cost table】 |
製品の原価を構成する要素(原価要素)の項目を一覧表にしたもの。原価要素は、一般的には材料費、労務費、製造経費、一般管理費、支払利息などに分類される。これらの原価要素を生産数量、仕入数量、販売数量、在庫量、品質、生産・販売方式など、多方面から算定して表を作成する。これはコスト分析や価値分析の基礎的データとなるものであり、経営上のムダの発見や費用の効率的配分を可能とするためにも重要。 |
|
コスト・パー・サウザンド 【cost per thousand】 |
広告媒体の経費効率を測定するための概念。人口1000人とか世帯数1000戸に広告を到達せるためには経費はいくら必要であるかを示す指標。広告料金を分子に、到達読者(視聴者)x1000を分母として算出する。 | |
|
コスト・パフォーマンス 【cost performance】 |
一般的に投資金額(支払い金額)に対する効用、または価値。商品の購入に際し、価格と価値のバランスをよく考えるようになった消費者の購入態度のこと。消費者が商品選択をする際の価値尺度として、「まあまあの価格で、良質の商品を」という考えが強くなっている。このような、価格と品質とのバランス感覚をさしており、じっくり商品を見て必要度を点検するようになった最近の消費者の購入態度を示したものである。したがって、商品開発に際しては、品質・機能と価格とのバランスをよく検討し、いわゆるリーズナブル・プライス(相応な値段)の商品、消費者を納得させ得る商品開発が、一層重視されなければならなくなっている。 | |
|
コスト・プラス法 【cost plus approach】 |
製造原価説、生産説、仕入れ原価説ともよばれる。価格決定方式のひとつで、原価に一定比率のマージンをプラスして売価を決定する方法。取扱商品の種類が多く、個々の商品に要するコストを試算することが困難な卸売業や小売業でよく採用されている方式であり、仕入原価に過去の実績や業界の慣習などを考慮して売価を決定する。成熟市場の今日では、このような売り手の論理を優先した価格設定のしかたに、やや疑問がもたれている。 | |
| コスト分析 | コスト・テーブルを基礎として、原価の構成を検討し分析すること。資材の調達・管理、仕入管理の科学化・合理化を目的とするものであり、対象品目の価値を認定し、その価値に対して適正なコストか否かを分析する。最小のコストで最大の価値を得ようとすることが基本的な考え方であるが、具体的にはある一定の価値(機能)を満たすための最小コストの構成の検討、あるいは逆に限られた予算で最大の価値を得るためのコスト構成の分析などに用いられることが多い。 | |
| コダ | 誇大広告 | 誇大または虚偽広告について、軽犯罪法第1条34号に「公衆に対してものを販売し、もしくは頒布し、または役務を提供するにあたり、人を欺き、または誤解させるような事実を上げて広告する行為」の処罰規定がある。特に生命に関係のある医薬品などについては、薬事法第66条にその効能などについての誇大広告に関する特別規定を設け、2年以下の懲役、もしくは10万円以下の罰金、という思い刑を定めている。 |
| コテ | 固定客 | いつも購入している商品(たとえば野菜、お肉、魚など食料品)、ある特定のブランド(たとえばフェラガモ、ピンクハウス、化粧品など)であれば決まって購入する店をもっている顧客がいる。その顧客を固定客と定義される。販売計画、プロモーション計画、売上予測を立てるうえで、あるいは売上を安定させるのに最も大切な客である。固定客が離反するようになると店の危険信号である。クリーンネス、鮮度、品揃え、価格、品質、的確な商品情報、接客、アフターサービスが固定客維持の重要な鍵になる。 |
| 固定費 | 経営活動によって発生する費用と獲得される収益(売上)との間に、ある種の関係がある。収益(売上)を増加させると、それに比例して増加する費用もあれば、収益(売上)を増加させてもこの収益(売上)の増加に影響を受けることなく一定に固定されているものもある。前者を変動費といい、後者を固定費と呼ぶ。したがって、固定費は操業度(売上)に関係なく固定的である費用部分を指す。具体的なものとしては、利子、地代、減価償却費、保険料、租税公課、電力・ガス・水道・電話などの基本料金、人件費も固定費として扱うことが多い。 | |
| コデ | コーディネート・セリング | 消費者欲求の個性化、多様化の進展はとどまるとことを知らない。これに伴い、マーチャンダイジングも消費者・生活者の生活のトータル・デザイナーとして時点の持つ店格、品格、価格を自らコーディネートする必要がある。単なる単品の組み合わせではなく、顧客のライフ・ステージと、それぞれの生活欲求に適合できる品揃えからユニット(単品)同士の構成を考えたコーディネート仕入れの実施に力点を置くことが大切となってきている。 |
| コピ |
コピー・テスト 【copy test】 |
広告効果を測定する方法の一つで、広告制作物を複数用意しておき、広告コピーやデザインについて、どれが最も注目され、どれが購買意欲をそそるか、どれが目標達成に効果的であるかなど、あらかじめ一部の消費者を通じてテストすること。事前テストと事後テストがある。事前テストは広告の計画段階において、コピーをテストしもっとも効果的なものを選定するための情報提供をするために行われる。アイ・カメラ法、プログラム・アナライザー法、判定テスト法などがある。事後テストは広告コピーを露出後に、設定された目標を効果的に達成したか否かを測定するために行われる。売上高テスト、記憶法、クーポン・テスト、注目率調査などの方法がある。 |
|
コピーライター 【copy-writer】 |
広告文案をつくる人。広告制作をするのに、アート・ディレクター、デザイナー、イラストレーターなどと協力して、コピー部門を担当する。テレビ・ラジオの文案をつくる人をCMライターと呼ぶ場合もあるが、通常、広義に両者を含めてコピーライターといっている。コピーは広告の中心であり、イラストレーション、レイアウト、カラーなどデザイン感覚にも深い知識を持つとともに、真に商品を売るためのコピーをつくるために、マーケティングにも精通しなければならない。また判断の客観性を保つために、コピー・テストをはじめとする調査結果を駆使する能力も必要である。 | |
| コホ | コホート分析 | 時系列的なデータの分析法であるが、単にトレンドを延長するのではなく、データを動かしている変動因を分析するところに特徴がある。牛乳の消費量だとか生活価値観を年齢別に集計した時系列データは、年齢の影響、時代の影響、同じ時期に生まれ育った世代の影響などで変動するものと思われるが、このうちの世代の影響をコホートと呼んでいる。これらの変動因を計量的に分析することにより、従来経験的に理解されていた世代別販売戦略、たとえばヤング戦略、アダルト戦略といった対象別戦略が、効果的に策定できるようになった。 |
| コポ | コーポレート・アイデンティティ | 企業による広告及びPRには自社の製品やサービスそのものの特性を強調し、効用を伝達しようとするものと、機関すなわち組織体そのもの名声と信用度を高め、一般大衆からの好意と愛顧を獲得するために行われる情報提供とがある。消費者の権利が明らかとなり、コンシューマリズムが台頭してくるにつれ企業は、社会的責任の遂行や公共性の発揮といった思想や基本態度を表明し、顧客・近隣・コミュニティさらに社会全般とのあいだに良好な関係を築こうと努力を重ねている。そのため企業のイメージづくりにサインやシンボル・マークを作成したり、行事や催し物を企画する。何よりもその企業の経営理念や基本方針は社会からの共感を呼び、社会との一体化を則すものであることが大切である。 |
|
コーポレート・ 【corporate communication】 |
企業全体を社会や消費者に認識してもらい、マーケティング上の戦略にしようというもの。商品の差別化戦略がいまひとつ効力を弱めている昨今、マーケティング活動は販売に直結する活動とともに、企業そのものを消費者やユーザさらには社会全体に売り込み、印象づけることの重要性が認識されるようになってきている。それがコーポレート・コミュニケーション(略称CC)であり、CC活動は、企業の広報活動や企業広告を中心に、工場開放、文化的行事、地域社会への貢献、エコロジーへの取り組みなどといった形で実践されている。 | |
| コミ |
コミッション・セールス 【commission sales】 |
売上高を基準として、歩合給や手数料(コミッション)を受けとり、原則として固定給というものがないセールス活動への報酬制度。歩合販売制度ともいう。 |
| コミュニケーション | 人と人の間で情報が授受され理解される過程をいう。ある個人が他の個人の態度を条件づけるために刺激を伝達する過程。言葉や電波媒体、新聞・雑誌などの印刷媒体などで伝達される。経営管理上のコミュニケーションは、計画の実行や達成する調整目的で行われるものと、参加意識などの動機づけを目的とするものとに分けられる。 | |
| コミュニケーション経路 | コミュニケーションは人から人へ情報の流れを通して動いている。発信者から媒体を等して受信者へという流れがコミュニケーション経路という。コミュニケーション経路は水平的経路、垂直的経路、公式経路、非公式経路などある。 | |
|
コミュニティ・マート 【community mart】 |
買物施設・飲食施設という商店街機能に公共施設を充実させ、地域住民に憩いの広場を提供しょうという、地域性を強調した未来型の商店街づくり。地域住民の商業地域に対するニーズが買物欲求ばかりでなくなっているところから、コミュニティ施設を併設する商店街近代化計画に強い関心が寄せられ、集会場や文化施設、産業会舘、消費者センターなどを導入する複合商業施設。 | |
|
コミュニティー・リレーション 【community relations】 |
企業が、周辺のコミユニティ(地域社会)との良好な関係を保つこと。企業施設を地域に開放したり、あるいは周辺居住者を優先して工場に雇用する、地域と共同で催しものをやるなど、多様な活動が考えられており、パブリック・リレーション活動の重要な活動の一つとして設定されるようになっている。企業全体を売り込むことによって、経営や営業活動を円滑に進めようとする、総合戦略の一環として行なわれるもの。 | |
| コル |
コールド・チェーン 【cold chain】 |
生鮮食品など低温・冷蔵・冷凍のまま生産者から消費者の手にとどけるためのシステムのこと。低温流通体系と訳されている。農産物や水産物のように生産に季節性のあるものは、一般に価格変動が激しく、生産・販売・消費の各段階で大きな問題であったが、この「低温の鎖」により貯蔵・運搬・販売が結ばれることによって問題が解決する方向に向かっている。その背景には、低温倉庫、冷凍・冷蔵車、冷凍ショーケース、家庭用冷凍・冷蔵庫の進歩、普及があったことはいうまでもない。 |
| ゴル |
ゴールデンライン 【golden line】 |
買い物客の目線に来る商品棚の位置。 |
| コン |
コングロマーチャント 【conglo-merchant】 |
単一の流通資本で、多くの業種・業態の小売店をもち、多角的な経営を行う企業のこと。たとえば、百貨店、スーパー・マーケット、専門店、ホームセンター、コンビニエンス・ストア、レストラン、ファースト・フード、ショッピング・センターのデベロッパー、映画館、スポーツセンターなど、小売・サービス店舗を複合的に経営している企業をいう。 |
|
コンサルティング・セールス 【consulting sales】 |
客の購入目的や購入資金など、客の立場で相談に応じながら進める販売活動。豊富な商品知識と、顧客目的を的確に把握する能力が強く求められ、対面販売を重視する専門店が得意とする販売方法である。 | |
|
コンシューマリズム 【consumerism】 |
消費者主義、生活者主義とも呼ばれている。コンシューマリズムは消費者の基本的権利を守ることを主張する理念であり、哲学である。米国の弁護士ラルフ・ネーダーが大手自動車メーカーの欠陥車摘発運動を展開しだした頃からこのことばが広く使われるようになった。その形態としては、不買運動や有害食品の摘発、誇大広告や不当な価格引上げなどの告発などがあるが、わが国ではネーダー型の運動のことをコンシューマリズムといったり、消費者運動全体をコンシューマリズムということも多い。 | |
|
コンセプト 【concept】 |
マーケティング・コンセプト、広告コンセプトといった形で使用され、特定の商品や企業イメージについての差別化をすすめ、マーケティング戦略や広告作成に際して市場導入を容易にするための主張・理念をさす。このコンセプトによって、具体的にマーケティング活動が展開されることが期待されるため、コンセプト・リサーチ(コンセプト決定のための市場情報収集)などにより慎重に決定される必要がある。広告の表現から始まったコンセプト・ワークは、今日では、新商品発売、商品のリニューアル、流通チャネルの活性化など重要なマーケティング戦略の決定に際して設定されるようになっている。 | |
|
コンセプト・テスト 【concept test】 |
新製品を開発する場合に、対象となる消費者がその製品コンセプトをどれだけ受けいれるかをテストすること。テストは、つぎのような質問で行なわれる。コンセプトの理解度、競合商品への優位性、コンセプトに対する共感と好意、購入意欲、ニーズとの適合性、製品に対する意見や不満、価格。テストの結果によって、販売活動のための貴重な情報や示唆を得ることができる。 | |
|
コンティニュアス・ 【Continuous Replenishment Program】 |
ベスト・プラクティス・ワーキング・グループの定義によると、従来の効率と経済性に重きを置いた小売業からの一括発注方式による商品補充から、実需要と予測商品需要にもとづいて補充を行うサプライチェーン内関連グループの連携作業であるとしている。商品を頻繁に、そして必要に応じて出荷することによって、在庫レベルの削減とオペレーティング・コストの減少となる。通常、小売業側は倉庫の在庫状況、および店舗から発注状況を毎日取引先に通知し、取引先は小売業からの出荷要請に常に対応する責任をもつ。 | |
|
コンテナリゼーション 【containerization】 |
一定の規格のコンテナ(荷役容器)に物品を積み込んで、荷役・輸送することをいう。これにより荷役の機域化・スピード化が可能となり、輸送コストも大幅に削減できる。バレチゼーションとともにユニット・ロード・システムの代表的方式で、コールド・チェーンの進展などにも欠かせない方式である。またこの方式によって陸・海・空の一貫輸送が可能になり、コンテナの国際標準規格が定められるに至っている。 | |
|
コンテント・アナリシス 【content analysis】 |
内容分析ともいう。新聞・雑誌の記事など言語的な情報を、たとえば消費性向など一定の分析視点にそって分類・集計し、流れの変化を追う方法。従来は記事などの切り抜きといった手作業を中心に進めていたが、最近ではコンピュータのデータベースの進歩によりつぎのようなアプローチが可能となった。すなわち、自由な発言をテープに録音し、そのプロトコルをディスクに入れ、内容検索コードおよびライフスタイル分類なども加えてファイルをつくる。これは「定性的」調査データ・バンクであり、重要な販売市場情報として活用することができる。 | |
| コンバージョンレート | 来店客数のうち、購入者が何人いたかという割合。 | |
| コンパースの法則 | 米国の経済地理学者コンパースがライリーの法則の検証を続ける中で明らかにした商圏の分岐点に関する法則。二つの都市商圏の分岐点を、商圏人口をベースにした方程式で算出するもので、店舗を構えた場合の販売地域設定に利用できる法則である。 | |
| コンバーター | 米国の繊維業界で発達した独特な問屋業。原糸生産から始まって、紡績、染色、デザイン、縫製、販売など繊維の生産から加工、販売までのさまざまな分野の業者を組織化し、流行に合った製品の製造・販売のためのコントロール機能をもっている問屋のことをいう。流行という極めて不確実な要素によって大きな影響を受けるとともに、生産から加工・販売まで多工程を経る繊維業界ならではの問屋機能といえるが、今後の問屋の流通機能における役割を示唆しているともいえる。わが国の繊維業界においては、商社の一部や大規模問屋がコンバーター的役割を果たしている例も見受けられるが、完全なコンバーターに育つまでには至っていないのが現状である。 | |
|
コンビニエンス・ストア 【convenience store】 |
食品や日相雑貨を中心とした品揃えの小売業態。大規模小売店や専門店などが提供できないような4つの便利さを顧客・生活者に提供する最寄り品を中心とする小売店といえる。4つの便利性とは、買い物の時間的便利性、場所的便利性、商品的便利性、人間味のある包容力・便利性。 | |
| コンビネーション・ストア | スーパーとディスカウント・ストアなど業態の異なる店舗を同一敷地内に隣接して立地させたり、同一建物内に配置したりする総合店舗をいう。品揃えの拡大だけでなくサービスや機能面においても多様化させることによってワンストップ・ショッピング機能の充実をはかるもの。 | |
|
コンピュータ・アシステッド・ 【CAO/CAR】 |
CAOベスト・プラクティス・サブコミッティの定義によると、POSデータにもとづく販売動向、季節変動等外部要因、実在庫情報、商品受領予定、許容安全在庫レベルに関する統合化された情報をコンピュータで処理することによって、店舗発注を事前準備するシステムとなっている。このシステムの成功は、在庫レベルとPOS販売情報の正確な把握による。 | |
|
コンビネーション・セール 【combination sale】 |
いくつかの商品を、ワンセットにして販売すること。コーヒーとクリーム、多種類の調味料、ウイスキーとグラス、ソーメンとソーメンつゆなどのように、関連商品を組み合わせ販売方法。中元や歳暮のギフトセットもコンビネーション・セールの一形態である。 | |
|
コンフィデンス 【confidence】 |
データマイニングの際の相関分析の指標のひとつで、ある関連購買における信頼度を表す。たとえば砂糖について卵の関連購買でコンフィデンスが70%の場合、砂糖購入者のうち70%が一緒に卵を購入する傾向があることを示す。*リフト値、サポートをご参照ください。 | |
| ゴン |
ゴンドラ・セールス 【gondola sales】 |
ゴンドラ(移動可能な陳列用具)を利用して、特別なプロモーションをするセールスをいう。商品を陳列したゴンドラに販売員をつけて試飲・試食をさせたり、見本を配ったりのプロモーションや、特別に目立つPOPを使って商品への注目度を高めたりする。新製品の発売時など、商品の知名度が低い時期にその知名度を積極的に高めたい時によく活用される方法である。 |